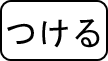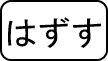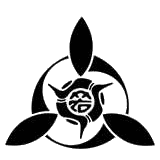-
カテゴリ:今日の給食
2月24日の給食 -
今日は、「きくらげ」のお話をします。
きくらげは、海にいるくらげの仲間ではありません。食べると、クラゲのようなコリコリした食感がすることから、この名前がついた、きのこの仲間です。料理に使われているきくらげは、乾燥させたものを水で戻して使うことがほとんどです。
栄養は、みどりの仲間で、体の調子を整えてくれます。今日のマーボー大豆に入っている、小さい黒いものが、きくらげをきざんだものです。公開日:2026年02月24日 11:00:00
更新日:2026年02月26日 08:26:00
-
カテゴリ:今日の給食
2月18日の給食 -
今日は、6年生が家庭科の勉強で考えてくれた給食メニューです!大人気のわかめごはんや、魚のたつたあげなどを組み合わせた、和食の給食を考えてくれました。
和食は、私たちが昔から受け継いできた食の文化です。世界的にも、そのすばらしさが認められ、2013年に、ユネスコの人類の無形文化遺産に登録されました。
和食の特徴の一つに、「だし」があります。「だし」とは、昆布や削り節などを、煮出した汁のことで、香りがよく、「うま味」があるので、うす味でもおいしく感じられます。今日のぶた汁も、「だし」を使って作りました。公開日:2026年02月18日 12:00:00
更新日:2026年02月19日 18:11:58
-
カテゴリ:今日の給食
2月17日の給食 -
今日は、白菜のソテーに入っていた「たもぎたけ」のお話をします。
たもぎたけは、切り株や倒木に生えるきのこですが、生える木の種類が決まっていて、ハルニレ(アカダモ)やヤチダモであることから「たもぎたけ(タモの木に生えるきのこ)」の名前がつきました。人工栽培もおこなわれていて、「ゴールデンしめじ」という名前で売られていたりします。
たもぎたけの栄養は、緑の仲間で体の調子を整えて病気にかかりにくくしてくれます。公開日:2026年02月17日 11:00:00
更新日:2026年02月18日 09:43:26
-
カテゴリ:今日の給食
2月13日の給食 -
今日の給食は、チョコレートのつぶつぶを入れたチョコレートケーキを作りました。
チョコレートの主な材料は、カカオ豆です。チョコレートのほろ苦さや香りは、カカオ豆のものです。カカオ豆は、それだけでは苦い味ですが、豆を砕いてどろどろにし、そこに砂糖などを入れて、甘いチョコレートができます。
チョコレートの栄養は、黄色の仲間で体を動かすエネルギーになります。公開日:2026年02月13日 10:00:00
更新日:2026年02月13日 14:55:30
-
カテゴリ:今日の給食
2月12日の給食 -
今日は、ブリの照焼がでました。
ぶりは、大きくなるまでに何度か呼び名が変ります。昔、武士や学者は成長の節目や、偉くなったときに名前を変える習慣がありました。その習慣のように「成長すると、出世するように名前が変わる魚」を出世魚と呼びます。ぶりもその一つです。出世する、ということで、縁起の良い食べ物と言われていました。
今日は、ぶりを照り焼きにしました。公開日:2026年02月12日 11:00:00
更新日:2026年02月13日 14:55:24
-
カテゴリ:今日の給食
2月10日の給食 -
今日は、おからふりかけがでました。
大豆から豆腐を作るとき、豆乳を絞って作りますが、絞ったあと残ったものが「おから」です。
おからには、「雪花菜」(きらず)という不思議な別名もあります。おからは白いので、雪にみたてた漢字をあて、読み方は、切らないでも料理できることから「きらず」と読んだという説があります。公開日:2026年02月10日 13:00:00
更新日:2026年02月13日 14:55:15
-
カテゴリ:今日の給食
2月9日の給食 -
今日は、「はっさく」のお話をします。
はっさくは、江戸時代に広島で発見されました。甘味と酸味(すっぱい味)の両方があり、中にはすこし苦みを感じるものもありますが、とてもいい香りがします。12月頃から収穫がはじまりますが、そのままでは酸味が強いので、1~2ヶ月おいて、すっぱい味がほどよくなってから売られています。
栄養は、みどりの仲間で、体の調子を整えて病気にかかりにくくしてくれます。公開日:2026年02月09日 15:00:00
更新日:2026年02月13日 14:55:09
-
カテゴリ:今日の給食
2月6日の給食 -
今日は「こんにゃく」の入った肉じゃががでました。
「こんにゃく」は、こんにゃく芋から作られます。土の中に直径3センチくらいの種芋を植えると、3~4年後に大きな芋になります。この芋から「こんにゃく」を作ります。
こんにゃくの中には、マンナンという食物せんいが入っています。食物せんいは、おなかのそうじをしてくれるので「からだのそうじ係」ともいわれます。
今日の肉じゃがのにんじん、じゃがいもは相模原市内産です。公開日:2026年02月06日 11:00:00
更新日:2026年02月13日 14:55:03
-
カテゴリ:今日の給食
2月5日の給食 -
今日は「サンマーメン」のお話をします。
サンマーメンとは、どんな料理でしょう?魚のサンマがのっているラーメンではありません。中国語で、「サン」が、「新鮮でしゃきしゃきした」という意味で、「マー」が、「上にのせる」という意味。つまり、新鮮な肉や野菜を炒めて麺の上にのせた、という意味で「サンマー麺」と名づけられたそうです。中国語を使っていますが、実は、神奈川県横浜市で考え出された料理です。とろみがついていて、麺に味がよくからみます。
今日のサンマー麺には、相模原市内産のキャベツが使われています。公開日:2026年02月05日 11:00:00
更新日:2026年02月13日 14:54:57
-
カテゴリ:今日の給食
2月4日の給食 -
今日は、三つ葉の入ったかき揚げがでました。
みつばは、日本に古くからあった植物で、その名の通り、1本の茎に3枚の葉がついています。大昔は野生のみつばを食べていましたが、江戸時代あたりから栽培したみつばを食べるようになりました。
みつばのさわやかな香りは、食欲を高めたり、イライラ解消に役立ったりするそうです。
公開日:2026年02月04日 12:00:00
更新日:2026年02月13日 14:54:51